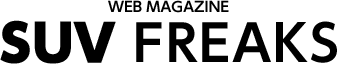プロモーション
シティユースとアウトドアのクロスオーバー、スズキ エスクード
小型車のイメージの強いスズキの中で、フラッグシップSUVとして長きにわたり君臨するのが「エスクード」です。シティユースとアウトドアのクロスオーバーを先駆けて取り入れたクルマで、現行モデルではほとんど本格クロスカントリーの要素がなくなってしまいましたが、3代目まではクロカン要素の強い走りのクルマでした。このエスクードについて紹介していきます。
更新日2019/04/15クロカンでもワゴンでもない、エスクードというカテゴリー

エスクードが発表されたのは1988年。時代はRVブームの勃興期で、SUVというジャンルはまだ確立していませんでした。そんな中、剛性の高いラダーフレームシャシーに、FRレイアウトのパートタイム4WDシステムを組み合わせたエスクードが誕生しました。
それまでクロカン色が強く、排気量も大きかった4WD車市場に、オンロードでも快適で燃費にも優れ、悪路走破性も確保したエスクードは、広くユーザーに受け入れられました。
当初は3ドアモデルのみでしたが、人気の上昇にともない、5ドア5人乗りや、7人乗り仕様も追加され、軽自動車や小型車のイメージが先行するスズキのなかで、フラッグシップカーとして成長していきました。
そんなエスクードの最初の転機は、2005年に発表された3代目のときに訪れました。
シャシーをラダーフレームから、ビルトインラダーフレームへと変更し、デフロック機構、副変速機付きの4輪駆動システムなどで性能を補強。ATばかりのライバル車に対して、MT仕様があったのもクルマ好きの心をくすぐりました。
モータースポーツシーンでも活躍し、パイクスピークやパリダカなど、耐久性やノーマルモデルの悪路走破性が求められるステージで結果を残しています。
スズキ勤め人が比較!エスクードとSX4 S-CROSSってどっちが買い?
4代目はシティ派コンパクトに変身

2014年、4代目の発表にともなって、3代目はエスクード2.4と改名して販売が継続されました。
4代目は同じハンガリーのマーシャルスズキで生産されていたSX4 S-CROSSと共通設計となり、3代目まで続けてきたFRレイアウト、ラダーフレーム構造を廃止。FFレイアウトを基本としたコンパクトシティSUVへと転身しました。
ボディは、全長4,175㎜×全幅1,775㎜×全高1,610㎜に縮小。エンジンもダウンサイジングの1.4Lターボとなり、エンジン排気量、ボディサイズともにSX4(S-CROSS)が上回り、関係性が逆転しました。
とはいえ、インテリアには本革とスウェードのシートに、遮音性の高いガラスを装着するなどした内装の高級感や、エンジンの出力ではSX4 S-CROSSよりも上質で、フラッグシップという位置づけは変わっていません。
安全装備は、デュアルセンサーブレーキサポートを始めとしたスズキの予防安全技術を満載。高レベルの安全性を実現しています。
また電子制御4WDシステム、4モード走行切り替え機能、車両運動協調制御システムという3つのテクノロジーで構成されるスズキ独自のALLGRIPを採用。高い走破性と走行安定性を併せ持っています。
3代目までのイメージは薄れてしまったものの、長距離のオンロードをクルージングも得意とする高性能かつ高機能なSUVに仕上げられた4代目エスクード。フラッグシップとして、時代の変化を敏感に感じ取り、アジャストする柔軟性も、エスクードの魅力なのかもしれませんね。