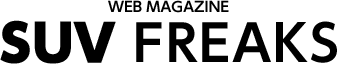プロモーション
90年代を代表するクロカン、三菱 パジェロの歴史を紹介
三菱 パジェロは、1982年の初代から30年以上、三菱の本格クロスカントリー車としての地位を譲ることなく、高い性能を受け継いできました。今回は、改めてパジェロの魅力と、その性能の高さを解説していきます。
更新日2019/04/10鮮烈なデビューだった初代パジェロ

本格クロカンとして、メーカー肝いりで1982年5月に販売が開始された初代パジェロ。フロントミッドシップにエンジンをマウントし、前後重量配分が50:50になるように設計されたパジェロは、当時としては非常に先鋭的なクルマでした。
剛性の高いラダーフレームを用いたシャシーに、メタルトップとキャンバストップの2ドアボディは4ナンバー登録のみ。翌1983年に全長4,650㎜のロングボディの5ナンバーエステートワゴンが追加されました。このエステートワゴンは、最大8名までの乗車が可能な広い車室内に加えて、サスペンションや4輪駆動システムにもこだわり、高い悪路走破性能を実現していました。
パジェロの代名詞となったパリダカールラリーへは、1983年に初参戦。市販車無改造クラスでデビューウィンを果たしました。
ちなみにパジェロのパリダカールラリーは、総合優勝12回、市販車改造部門では13回、市販車無改造部門では9回の優勝と、他メーカーの並み居る本格SUVクロカンを抑える偉大な成績を残しています。
1991年にフルモデルチェンジ

1991年にフルモデルチェンジを受けた2代目は、ラダーフレームや足回りなどを初代から受け継ぎつつ、各部にリファインを施したモデルです。エンジンは、当初3.0L V6ガソリンと2.5Lディーゼルのインタークーラーターボでしたが、1993年のマイナーチェンジで3.5L V6ガソリンと2.8Lディーゼルインタークーラーターボ、1996年には2.3Lの直列4気筒ガソリンをそれぞれ追加。さらに、1997年の改良で3.5L V6エンジンに世界初となる直噴機構GDIを搭載しました。
“広くて使いやすい”“高トルクで乗りやすい”というパジェロの特徴は、初代から現代まで変わらず引き継がれています。
オンロードでの走行性能も高められた3代目

1999年に登場した3代目は、“新世代の世界基準パジェロ”のコンセプトのもと、それまでのクロカン性能を残したまま、舗装路での操作性や走行性能を高めたSUVとして進化しました。
シャシーとボディに大きな変革があり、新開発のラダーフレームビルトインモノコックボディを採用。これは、従来まで剛性が低く本格クロカンには向かなかったモノコックボディを、ラダーフレームへ溶接にて取り付けることにより、ボディ剛性を上げて強度・耐久性を高めたものです。さらにデザインの自由度が増し、かつ軽量化にも成功しました。
これにより3代目は、優れた操縦安定性と乗り心地を両立させたモデルとなり、実質的な三菱のフラッグシップカーとなっていきます。
4代目はシティ派SUV路線に変化

4代目への進化は2006年のこと。悪路走破性の高さを守ったまま、シティ派SUVとしての性格をより強めました。
フロント220mm、リア260mmというサスペンションストロークを確保しながらも、電子制御システムや高度な4WDシステムが、オンロードでの走行安定性に貢献していました。その豪華な内装やしっとりとした乗り心地は、特筆に値するものでした。
その後、2019年まで幾度かのマイナーチェンジを行っているのですが、フルモデルチェンジから13年が経過。さすがに設計が古くなってきたところに、各国のモーターショーでパジェロの新型らしきコンセプトカーが登場しました。もう一度、本格クロカンSUVの復権に貢献するのか、楽しみですね。
多人数乗車が可能なパッケージに、悪路走破性とシティユースいずれも優れた性能を発揮するパジェロですから、新型が発売されれば日本国内はもちろん海外市場もほうっておくはずがありません。三菱の動向には、パジェロファンのみならず世界中のSUVユーザーがかたずを飲んで見守っています。